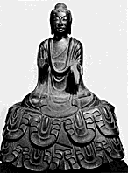
銅像如来座像
四十八体仏
法隆寺に伝わった、飛鳥時代から天平時代にわたる小金銅仏59体。なかには、1l世紀に橘寺から移されたものも含まれている。現在は東京国立博物館蔵。なお、48という数は阿弥陀の48願に結びつけたもの。
|

銅造摩耶夫人及天人像
(四十八体仏のうち)7世紀前半摩耶(まや)夫人の脇の下から釈迦が誕生する情景を表した群像である。インド以来、釈迦の理想的な姿である仏像のほかに、釈迦の生涯(仏伝)を表現した絵画や彫刻も信仰された。我が国ではめずらしいものである。
|
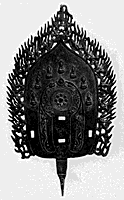
銅像光背
(四十八体仏のうち)甲寅(こういん)年(594年か654年)に、王延孫が造った釈迦像の光背、中尊と左右の菩薩とをつつみこむ、一光三尊式の光背である。小さな仏と天人とをつけたこのような光背は、飛鳥大仏や法隆寺金堂の釈迦如来など北魏の系統をひく仏像に多く用いられた。
|