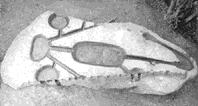
岡酒船石
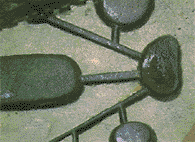
岡酒船石
|
史跡
長さ5.3m 7世紀 明日香村 岡
上の面に円や楕円の浅いくぼみを造って、これを細い溝で結んでいる。江戸時代には、「むかしの長者の酒ふね」とよばれた。酒をしぼる槽(ふね)とも、あるいは油や薬を作るための道具ともいわれている。しかし、この石の東40mのやや高いところで、ここへ水を引くための土管や石樋がみつかっていることから、庭園の施設だという説もある。なを南西400mの飛鳥川東岸で、組み合わせて水を流すようにした石が2個掘り出されており、これにならって、やはり酒船石とよばれている。この方は、現在、京都にある。最近の調査で岡の酒船石周辺を取り巻く石垣と大規模な土木工事のあとが見つかり、斉明天皇の両槻宮との関わりが注目されている。
|