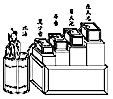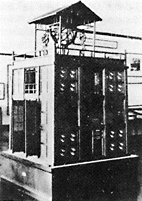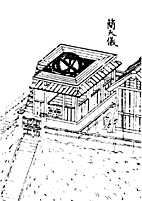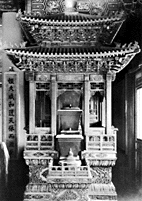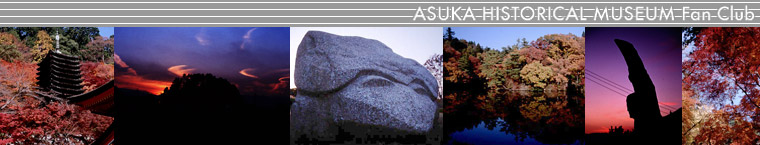
|
|
水落遺構は水時計を置き、おそらくは時を知らせる鐘楼をも兼ねていたであろうと考えられた。あるいは天体観測をも行なっていた可能性も考えられる施設であるが、実際にそれがどのような建築であったかを復原するには多くの問題がある。 それは、遺構の性格が、これまで知られている古代の寺院や宮殿、住居などとはまったく異なるものだからである。平面は正方形であって、基壇周囲は斜面になり、しかも綿密な貼石がなされている。柱は一辺4間の総柱風であるが、中心には柱がない。基壇中央に水槽があり、地下には木樋や銅管が埋設されている。こうした平面の形式や機能からは、ここに想定される建物が、多くの人間が出入りするものではなく、機械設備を置く施設に近いことが示唆されよう。しかし、それにしては周囲の化粧がただごとではなく、むしろ宮殿楼閣にふさわしいようでもある。あるいは、このようなものを「台*と称したのであろうか。 一方、柱そのものの建立方法も、地下に柱座のある礎石を埋めて、いわば礎石と掘立てを兼ねていると言える特殊なもので、いうまでもなく飛鳥時代初期の塔の心柱の形式に等しい。これは、柱がかなり高く、しかもそれだけで自立しうるはどのものであったことを示していよう。礎石を用い、しかもそれらを相互に石でつないでいるのは、柱の移動と沈下を防止したものと判断され、上部構造が微動だにしないほどの精密さが要求されていたことを想像させる。このように構造的にみても、この遺構を復原するにあたっての指針は、人間のためというより、精密な機械のための建築という点にあるように思われる。 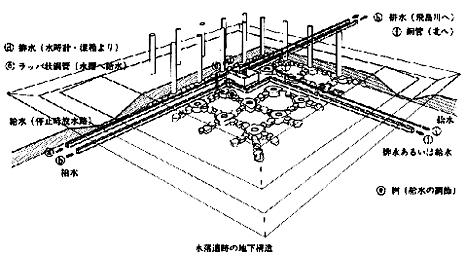 以上のことから考えうることは、第一に、建物がかなりの高さを持つということである。しかし、高いといっても、往座や柱痕跡から、柱は本径で40cmを越えないので、五重塔や、50mに及んだといわれる復原出雲大社のような並みはずれた高さにはならないであろう。したがって、その規模は2層、具体的には、建物の高さは9mほどが限度であろう。この条件からは下層に水時計を置き、上層に鐘ばかりでなく、水運渾象などを置くようなことも可能である。第二に、屋根は瓦葺でないことは確かであるから、板葺や草葺に類すると考えられる。その形式は平面からは宝形造が思いうかぶが、決定的ではない。第三に、外壁や柱間装置にいたってはまったく想像の域を出ないが、たとえば下層に漏刻を置いているのであれば保温や防塵のために、柱筋通り二重の壁体による厳重な閉鎖性が要請されるであろうし、一方、上層が鐘楼や、あるいは、天体観測の場であればなおのこと、これとは逆に開放的であることが必要になってくる。この点では、後の『延喜式』にみられる漏刻台の幔の記載などが思いうかぶ。 なお、時を知らせる鐘、鼓に関しては、直接、その形状を記録した史料に乏しい。ただ、鐘については、『廷喜式』の「陰陽寮式」に鐘の撞木の寸法が記されている。それによると、長さは1丈6尺(約4.8m)、周囲の長さ3尺(約0.9m)、つまり、太さ30cmほどの長大な撞木である。これに対応する鐘も、撞座が30cm以上もある巨大なものであったと推測される。「民に時を知らしむる」ための鐘も、やはり、これと同様にかなりの大きさを必要としたであろう。また、鐘は吊すものという考えからすると、現存する寺院の鐘楼の形態も、水時計建物の復原に、何らかのヒントを与えるのかもしれない。 本図録にかかげた復原図も、あくまでその一案にすぎない。ひるがえって、『日本書紀』において、水時計は「楼」でも「殿」でもなく「台*」に置かれたと記されていること、そして、現存する歴史的な天文観測施設は、中国では屋内でなく露出して置かれていることなどを考えあわせると、中国歴史博物館にある復原された北宋の水運渾天儀のような形式、あるいは絵図に残る江戸時代の天文台のような形式の建築も、上記の構造的な条件に矛盾せず、あながち復原像として否定し去ることはできないかも知れない。水時計の建物がどのようなものであったのか、ここに古代への夢がまたひとつ新たに加わった。
|
 Copyright (c) 1995 ASUKA HISTORICAL MUSEUM All Rights Reserved. Copyright (c) 1995 ASUKA HISTORICAL MUSEUM All Rights Reserved.Any request to kakiya@lint.ne.jp Authoring: Yasuhito Kakiya [K@KID'S] |